昨年度も、様々な取り組みや、教育に関する考察が行われました。2012年度の『授業と生徒作品』記事をカテゴリーごとにまとめました。最新の記事は、「授業と生徒作品」をご覧ください。
生徒作品と授業の報告
日々の授業の報告や、そこから生まれる作品の一部をご紹介します。

全般
- 『おはなし おはなし』 ~付箋を使ったより深い物語の読み方~
- 子どもたちがより絵本に親しみ、さらに作文の基礎も学べる、付箋をつかった新しい読書方法です。
- 「クライドルフの思い」Y君(小5)
- 小学五年生のY君が、『スイスの画家 クライドルフの世界』の展覧会に行ったと嬉しそうに報告してくれました。
- 書き言葉に慣れる ― Rさん(小4)・Y君(小5)の授業の様子から
- 教室に通う4年生のRさんと5年生のY君の授業の様子を紹介します。この日は、「スリッパと靴を比べよう」というテーマで授業をしました。
- 【ワークショップの様子】いろいろへんないろのはじまり!
- 作文ワークショップには、ただ「体験をして楽しい」というだけではない、そのワークショップごとの「思考のテーマ」や「文章技術のテーマ」があります。
- 個性に合わせた学習支援・中3T君の取り組み
- 教室では、特別な支援を必要とするお子さんの学習サポートにも取り組んでいますが、その際、マルチ能力理論の視点からお子さんの学習にアプローチしていきます。
- 読み聞かせから黙読へ――R君・小2の場合
- この半年でたくさんの絵本を楽しんできた小学二年生のR君は、とうとう一冊の物語に挑戦しました。今回は、R君の読書の様子をご紹介します。
観察

- 教室の観察 ― 小学5年生 Y君の初授業
- これからY君が学ぶ環境である教室をよく知ってもらうために「教室を観察しよう」というテーマで授業をしました。
- 【生徒作品】桜の観察(Rさん・小2)
- 桜の花を手にとり、見た目や触り心地、香りについて感じたことを言葉で表現すると同時に、観察の手順をまとめる練習をおこないました。
調べ学習・レポート
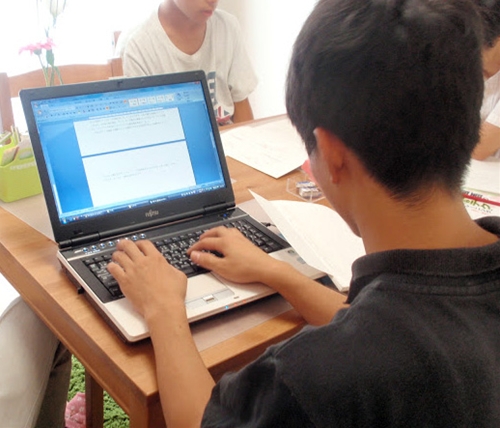
- 生徒作品 『ZARDの魅力』 (中3・A君)
- 今年の春から、日本の90年代ポップスを代表するアーティスト・ZARDの魅力にどっぷりと浸かったA君は、ZARDというテーマで作品制作をすることにしました。
- 【プロジェクトの紹介】落語紹介新聞(Y君・小5)
- Y君は、三遊亭圓窓師匠の下、月に数回落語の稽古に励んでいます。小学校では、芸術鑑賞会で、全校生徒を前に落語を一席講じたこともある、小さな噺家さんです。
- 【プロジェクト】『次期戦闘機(FX)におけるユーロファイターの優位性について』 中1・O君
- O君が好きなことは、国際関係のニュースを読むことです。現在の国際関係について豊富な知識を持ち、中でも、軍事についての知識は大人顔負けでした。
物語創作

- 絵本を読んで物語を書いてみよう ~五感で世界を読む力を身につける~
- 絵本に登場する動物たちから五感を研ぎ澄ませ方を学び、実際に自分のいる環境について、詳しく調べて物語を書いてみるという課題です。
- 【プロジェクト】物語を作ろう!
- 作家の視点を得ることは、子どもたちの成長において重要な役割を果たすのです。
- 【生徒作品】物語『空の精霊たち』小4・Yさん
- Yさんは、『びりっかすの神様』や『二分間の冒険』の作者・岡田淳さんの作品のような面白い話を書きたいと考えました。
- 【生徒作品】物語『やったーとりかえしたぜっ』(小3・Iさん)
- 「動物が活躍して、ドキドキハラハラする探偵のお話を書きたい!」そんな思いからこのプロジェクトをスタートさせたIさん。どんな物語にしようかと話し合っているうちに、次々に面白いアイディアを思いつきました。
- 【生徒作品】物語『クリスマスのナゾ』(小3・Yさん)
- 小学3年生のYさんは7歳の女の子チェリーが探偵となって大活躍する物語を書いてくれました
コラム
ことばや教育に関するコラムです。
理念

- 実体験をことばにする大切さ
- 「五感を通して感じた実体験を言葉にすることの大切さ」についてご紹介します。
- 小学校中学年の教育課題「書き言葉の習得」
- 書き言葉の習得には、話し言葉と同じように、それに浸る場=読み慣れ・書き慣れる環境が必要なのです。
- 【中学生の教育課題】論理的・形式的思考を本格的に学ぶ
- 中学生になると子どもたちは、論理的・形式的思考を本格的に学ぶ準備が整い、他者と意見を交わす術を学んでいきます。また興味・関心が高まり、さまざまな知識に触れ、教養を蓄えていく時期でもあります。
- ブッククラブを通して、大人も学び続ける
- 講師は教える者であると同時に、自身が学び続ける学習者でもあります。日常的なブッククラブを通して、交流し、議論を重ねながら教育に関わる知識・技術・それぞれの考えを高め合っています。
- 人生という物語
- 物語に触れ、自らもそれを創ることは、長いカリキュラムの中で大きな意味を持ちます。今回は、物語というものをさらに掘り下げ、そこから、学びとはどのようなものであるのかをお伝えしたいと思います。
読書・読み聞かせ

- なぜ読書? ―― 社会的な読書を目指して
- 読書の何が子どもを育てるのでしょうか。また、どうすれば読書の楽しさに気がつき、また本の世界を深く味わうことのできる子どもになるのでしょうか。
- 多読する ― 小学校中学年の読書
- 小学校中学年(3、4年生)の時期に確かな読書習慣を身につけ、数多くの読書経験を積むことが、その後の学びの支えとなります。今回は、小学校中学年の読書についてご紹介します。
- 絵本の読み語り・読み聞かせ ―― 物語を通して人生と向き合う
- 本は、それぞれの文化に蓄積された世界観や人生観といった価値観の縮図です。それらは文化の違いを越えて普遍的な人生の真理を私たちに垣間見せてくれます。
- 読書案内 『おはなし おはなし』
- こどもたちの気持ちを物語へぐっと引き込む、魅力的な語りからから始まるアフリカの民話には、「クモ男」といわれているものがたくさんあります。
- 読書案内 『むぎばたけ』
- 「五感を使って読む」というテーマで、本をおすすめするとしたら、私はこのアリスン・アトリーの『むぎばたけ』をおすすめします。
- 【本の紹介】『「大発見」の思考法』 iPS細胞vs素粒子
- 本書のおすすめポイントは、当教室が掲げている、「子どもたちが言語技術を習得することの重要性」について、科学者ならではの視点と言葉で語られているところです。
- 【本の紹介】『小さな町の風景』(杉みき子作/偕成社)――本をめぐる旅
- 11月下旬、『小さな町の風景』という物語の舞台となった、新潟県高田市(現、上越市)に、物語で描かれた風景をもとめて旅をしてきました。
受験
- 【受験と向き合う】 現代文 長文読解シリーズ 1
- 読解問題と読書のレベルには密接な関係があります。うまく解けない場合、過去問をひたすらやればいいというものではありません。
- 【受験と向き合う】 現代文 長文読解シリーズ 2
- 長文読解に必要な力である「分析的な読み」を習得するための試みのひとつ、「物語文を読み、自分で問題を作る」課題をご紹介します。
社会のニュースから
- MSN産経ニュース『7割が「漢字力低下した」 携帯、メール普及で』より
- 漢字だけでなく様々な日本語の表現が失われることは、私たちが複雑な現実の事柄を言い表し、それらと向き合う方法を失うことにつながります。
- 体罰の問題 ~指導者の役割と家庭での指導について~
- 学習の自律性を指導の核に置いている教室として、体罰について触れてみたいと思います。
アートメチエ
教室では、東京電機大学理工学部情報システムデザイン学系石塚研究室と連携し、社会人や中高生を対象とした教養講座を随時開講しております。

- 千住アートメチエ 文化教養講座『塔(タワー)とツリーの民俗誌』
- 。第一回のテーマ「塔(タワー)とツリーの民俗誌」では、塔(タワー)と木(ツリー)をキーワードに歴史をたどり、人々に受け継がれてきた技術と思いについて、お話し頂きました。
- 第二回 千住アートメチエ文化教養講座『一生に一度見たい!オーロラの魅力』
- 約30年に渡り北半球各地で、オーロラを撮影し続けてきた門脇久芳先生を講師にお招きして、美しい写真や映像、音声と共にオーロラの魅力や、科学的説明などわかりやすく解説していただきました。
- 第三回 千住アートメチエ文化教養講座『サンタクロースの民俗誌』
- 一人の聖人の物語が、各地の習俗と交わりながらどのようにして世界的な行事となっていったのか、また、各地にある死と再生の生命観について、参加者のみなさんと共に考えました。
- 第四回 千住アートメチエ文化教養講座『食の記号学――ワインと肉』報告
- ワインと肉を切り口に西洋の食文化と人々の思想について、参加者のみなさんと共に考えました。
読書感想文
読書感想文に関連した記事をご紹介します。
- 2012年 夏休み読書感想文のポイント (小学生編)
- 2012年 夏休み 教室からのおすすめ図書(小学生向け)
- 2012年 夏休み読書感想文のポイント (中高生編)
- 2012年 夏休み 教室からのおすすめ図書(中高生向け)
- 読書感想文特集 ~対話を通して楽しく書き上げる読書感想文の書き方
- 読書感想文は嫌なものではなくなるどころか、読書をより楽しむための、あるいは上質な学びためのきっかけになり得るのです。
その他
その他の活動をご紹介します。
2013年度も、様々な取り組みを行ってまいります。
リテラをどうぞよろしくお願いいたします。







