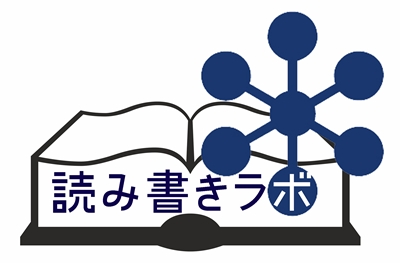
前回は、『順序立てた説明文の書き方』をお伝えしました。
今回は、「くらべる」説明文の書き方をお伝えします。
なぜ「くらべる」のか
あるテーマや物事について考えたり、説明したりする時には、他のものと「くらべる」ことが大切です。
「分かる」ということばは、「分ける」を源にしています。
「分ける」ためには、他のものとくらべて、その境界線を明らかにし、それがどのようなものかを明らかにしなければなりません。
くらべることは、その物事をしっかりと「理解する」ことにつながるのです。
今回は、そうした「くらべる」説明文の書き方をお伝えします。
考えるべきポイント
物事をくらべて説明する時、考えるべきポイントは、次の二つです。
- 同じところと違うところ
- なぜそのようになっているのか
それでは、くわしく見ていきましょう。
同じところと違うところ
同じところ
形・用途など、くらべる物同士の共通点を考えます。たとえば、くつとスリッパの比較であれば、次のようになります。
- 足にはいて歩くための物
違うところ
くらべる物同士のちがいを考えます。以下は、くつとスリッパのちがいの例です。
 |
 |
- かかとなど、各部の形状
- くつ: 足首の下全体を覆う形
- スリッパ: かかとの部分が開いている
- 素材
- くつ: 布、合成繊維、ゴム、頑丈な糸など
- スリッパ: 布、厚紙など
- はき心地
- くつ: 足の形にフィットする
- スリッパ: 足をしめつけない
それぞれの具体的なちがいについて、くわしく書きましょう。
順序立てた説明のしかたは、『順序立てた説明文の書き方』をご覧ください。
なぜそのようになっているのか
形・色・素材などの「理由」
くらべることで、そのもの独自の形・色・素材などがあるとわかりました。
それでは、そのものはなぜ、そのような形・色・素材なのでしょうか。
その理由を考えることは、ものの目的を考えることにつながります。
私達が普段何気なく使っているものにも、それがそのようになった目的があり、それを理解することが「分かる」ということなのです。
以下は、くつとスリッパの比較における、それぞれのちがいの「理由」の例です。
- かかとなど、各部の形状
- くつ: 足首の下全体を覆う形 → 激しく動いても脱げないように
- スリッパ: かかとの部分が開いている → すぐに脱いだり履いたりできるように
- 素材
- くつ: 布、合成繊維、ゴム、頑丈な糸など → 激しい運動や長時間の使用に耐えるように
- スリッパ: 布、厚紙など → 軽くするために 安くするために
- はき心地
- くつ: 足の形にフィットする → すぐに脱げないように 激しい運動ができるように
- スリッパ: 足をしめつけない → すぐに脱げるように リラックスできるように
作文例
これらをまとめると、次のような文章になります。
Y君(5年)の作文
「スリッパとくつの比較」
これからスリッパとくつの比較をする。
まずこの二つは、はいて使うことと、はいて歩くための物であることが同じだ。でも、スリッパは家ではくに対して、くつは外に出るときにはくことが違う。
一番のちがいは、かかとのあたりだと思った。くつは、かかとの部分をおおっているが、スリッパはかかとの部分は何もおおっていない。そのため、使っている素材の量もスリッパの方が少ない。
スリッパのくつ底の素材は、しっかり歩けるように平らにしてある。それにくつ底がかたいスポンジなので、歩きやすい。それに対してくつは、走るときに力を入れてダッシュができるようにおうとつのあるゴムになっている。
くつ底は、スリッパは糸が通っていたが、くつには通っていない。それにスリッパはふつうのさいほう用の糸を使っていたが、くつはかんじょうで切れにくい糸を使っていた。そのために、スリッパに比べてくつの方がこわれにくい。
最後にくつ底について、スリッパにはくつとちがって明らかにちがうところがあった。それは、中じきがはいっているかいないかだ。くつには中じきがはいっていて、くつ底もスリッパよりも高い。
このようなことから、スリッパは家の中で、ゆかをよごしたくない時などに使い、くつは外で、運動するのに適した形になっていることがわかった。
もちろん、自分とは違う理由・目的を考える人もいるはずです。
それは、それぞれの「視点」が存在するということであり、それらを共有することで、新しい発見ができます。
「わかった」つもりにならず、常に考えながら見る姿勢・聞く姿勢を促し、本当の「分かった」に結びつけていきましょう。
「教育コラム」の記事
イメージ力と学びの関係
イメージは学びの本質です。
教科を問わず、学習にイメージ力は欠かすことができません。
たとえば、算数・数学において、条件や数字、文章をイメージ化しなければ、問…
作文が書けない。本を楽しめない。あるいは、読解問題が解けない。算数・数学の文章題が解けない。
それはもしかすると、心の中に「イメージ」がつくれていないからかもしれません。
イメージ力不…






