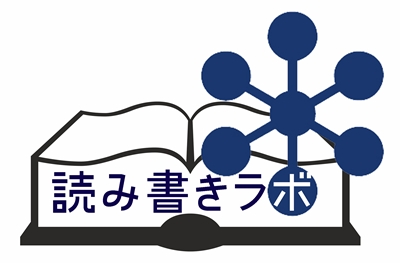
前回の記事では、小2後半~小3後半の読書についてお伝えしました。
今回は、小4~小5前半と、小5後半~小6にかけての読書についてです。
この時期の読書の理想は、「手当たり次第に読む」濫読です。
登場人物と同化してさまざまな時代・世界に入り込む読書体験は、幸せなものです。
また、そうした深い読書体験は、翻って、自分自身や社会を見直すことにつながっていきます。
小4~小5前半
物語と現実を行き来する
作品の世界に没頭できることが大切です。
特に、ファンタジーがおすすめです。異なる国・社会を思い描き、主人公に同化して様々な感情を追体験し、そうして本を閉じ、自分に戻ってきます。そうした体験を積むうちに、少しずつ、自分の生きる社会や自分自身を、より客観的に意識するようになってきます。
計画的な読書と生活を
この時期には、時間を決めた計画的な読書をおすすめします。
高学年になると、塾や習い事が増え、読書時間の確保が難しくなります。読書習慣を途切れさせないようにしましょう。
また、逆に、本に夢中になりすぎるのも考えものです。読書に夢中になるのはよいことですが、先を急ぐあまり早読みになってしまったり、寝不足になってしまったりするようでは、かえって読書から得られる体験を薄めてしまいます。
時間を決めて行動することは、学習をふくめ生活全体に良い影響があります。
毎日コンスタントに読み進めていくことで、過度な熱中や読書の空白を避けましょう。
この時期におすすめの本
 二分間の冒険 (偕成社の創作)
二分間の冒険 (偕成社の創作)体育館を抜け出した悟は、不思議な黒猫と出会い、竜の支配する世界に入り込みます。元の世界に戻るには、「一番確かなもの」を見つけ出さなければなりません。いつまでも色褪せない名作です。
小5後半~小6
テーマを読み取ること
ただ展開を楽しむだけではなく、物語に織り込まれた想い、すなわち「テーマ」を読み取ることが大切になってきます。
この時期は、登場人物が、周囲の環境や社会と対峙しながら、変化・成長する内容の物語が適しています。
すべての本に深いテーマがあるわけではありませんが、名作と呼ばれる作品には、批評にたえうるテーマが含まれています。
物語世界を楽しみながらも、より広い視野で人物の変化をとらえ、物語の本当の意味・深さを汲み取っていけるようになることが、この時期の目標です。
本は好きだけれど、読解問題の点が安定しない子は、この段階まで読書レベルが達していないことがほとんどです。物語世界の入り込みすぎて、ひとりよがりな解釈にならないよう、より広く客観的に文脈をとらえる読書力をつけましょう。
つながりのある読書
なお、こうした読みの質を高めるためには、物語のテーマに意図的に導く・気づかせることが大切になります。
ぜひ、複数人で感想を話し合い、自分とは違う解釈や感じ方を知りましょう。お父様・お母様が子供の頃に読み、心に残っている本を紹介してあげるのもよいでしょう。また、「後書き」を読むよう促しましょう。後書きには、作者・訳者のコメントがあり、物語の解釈のヒントになります。
また、気に入った作家を見つけたら、作品を横断的に読んでみましょう。
この時期におすすめの本
 モモ―時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にかえしてくれた女の子のふしぎな物語 (岩波少年少女の本 37)
モモ―時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にかえしてくれた女の子のふしぎな物語 (岩波少年少女の本 37)灰色の男たちに時間を奪われ、心を失っていく人々。モモは、みんなの時間を取り戻そうとしますが……。私達が忘れている大切なものに気づかされる一冊です。
未来のための読書習慣を
読書体験は、成長と共に深化していきます。
培われた「読む」力は、本を超え、社会や人を読む力となります。
生活と環境を整え、ゆっくりと、読書習慣をつけていきましょう。
次回は、「順序立てて説明する」ための文章の書き方についてお伝えします。
- 読書についてもっと知りたい:
「教育コラム」の記事
記述指導の真のゴール!不自然な「てつなぎ」を避け、「ポンコツロボ」にも伝わる論理的な解答文の作り方から、すべての教科に通じる構造読解力の育て方までを解説。
記述の採点基準は「ズーム(抽象度)」と「ピント(客観性)」で決まる!設問の条件と解答欄から情報量を逆算し、ポンコツロボにも伝わる論理的なキーワードを選ぶ技術を解説。
「内容が不十分」から卒業!物語文は【状態・展開・結末】、説明文は【抽象・具体】のフレームで過不足なく情報をまとめる、論理的な解答作成メソッドを紹介。











