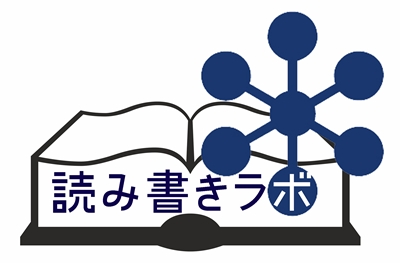
みなさんのお子様は、本を読んでいますか?
読書は、語彙や言葉の用い方を学べるだけではなく、自分とは違う視点を学んだり、今ではない・ここではない世界への入り口ともなります。
ただ、読書を長時間しているからといって、読書が学習に良い影響を及ぼしているとは限りません。読書時間ではなく、むしろ、読書好きかどうかが、学習に良い影響を与えることが明らかになっています。
読書を「好き」になるには、まず「楽しむ」ことが大切。
今回は、楽しむための読書をどのように進めればよいのかを考えます。
その読書、楽しめていないかも?
次のような様子が見られる場合、読書を楽しめていないかもしれません。
- 読み飛ばしている
- 読んだページ数や冊数・難易度にこだわる
- 同じ本ばかりを読む
それでは、詳しく見ていきましょう。
1. 読み飛ばしている
お子様が読書をしている時、ページをめくる速度が早すぎると感じたことはありませんか。
こうした場合、まず、しっかりと音読ができているかどうかを確かめましょう。
- 文末を読み飛ばす
- 行を飛ばして読んでも気づかない
- イントネーションがおかしい
音読の際に上のような様子が見られた場合、文章の意味を理解していない可能性があります。
音読の練習に戻り、「言葉を音にする」ことを意識しましょう。
その際は、一緒に読んだり、交互に読んだりするなど、音読を楽しむことを優先してください。また、物語について、さまざまな感想や意見を交換することをおすすめします。同じ本をうまく読めるまで読むよりは、さまざまな本をより多く読んでいく方がよいでしょう。
2. 読んだページ数や冊数・難易度にこだわる
学校などで読んだ冊数が貼り出されたりすると、とにかく読めば周囲に認められると誤解してしまうことがあります。
外からの評価を気にするようになってしまうと、読書本来の目的が変わり、「早読み」をしてしまう可能性があります。
冊数や読む早さ・難易度で評価する環境があるのなら、まずはそれを見直しましょう。
3. 同じ本ばかりを読む
これは一概に悪いことばかりとは言えません。
ただ、次のようなことに気をつけましょう。
- あきらかに簡単な本・絵ばかりの本を読んでいないか
- 新しい本が手に入る・借りられる環境や習慣があるか
同じ本を繰り返し読むことは、悪いことではありません。しかし、上記のようなことが考えられる場合、時間つぶしや多忙な生活からの逃避になっている場合があります。
読書時間を意識的に確保し、読書の環境を整えましょう。
読書指導で気をつけたいこと
それが間違った方法であれ、子どもたちは、「読書をしている」と思っています。
したがって、「読めていない」と言うだけでは、混乱するだけです。
それどころか、「読書好き」というアイデンティティを否定された反動で、読書嫌いになってしまう恐れもあります。
それでは、読書を楽しむためにはどうすればよいのでしょうか。
次回は、「読書習慣をつけるために大切なこと」をお送りします。
その他の「教育コラム」の記事
記述指導の真のゴール!不自然な「てつなぎ」を避け、「ポンコツロボ」にも伝わる論理的な解答文の作り方から、すべての教科に通じる構造読解力の育て方までを解説。
記述の採点基準は「ズーム(抽象度)」と「ピント(客観性)」で決まる!設問の条件と解答欄から情報量を逆算し、ポンコツロボにも伝わる論理的なキーワードを選ぶ技術を解説。
「内容が不十分」から卒業!物語文は【状態・展開・結末】、説明文は【抽象・具体】のフレームで過不足なく情報をまとめる、論理的な解答作成メソッドを紹介。




