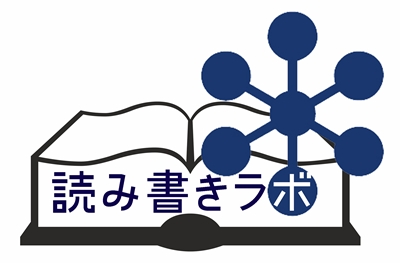
前回の記事では、幼稚園生から小1前半にかけての読書(読み聞かせ)についてお伝えしました。
今回は、小1後半~2年生前半の読書についてです。
小1後半~2年生前半
焦って一人読みに移る必要はありません。
内容理解だけでなく、読むことそのものについても、まだまだガイドが必要な時期です。
さまざまな絵本を楽しみましょう。
読み聞かせから一人読みの移行期については、前回の記事をご覧ください。
この時期の読書のポイントとしては、
- 読み方を知る
- 出来事をつかむ
- 因果関係をつかむ
が挙げられます。
1. 読み方を知る
この時期、子どもたちは、「読むとはどういうことか」を学びます。
正しい読書のあり方とは、まず、楽しむことです。
- 読み飛ばしている
- 読んだページ数や冊数・難易度にこだわる
- 同じ本ばかりを読む
などの様子が見られる場合は、読書の姿勢そのものを見直す必要があります(詳しくは、『その読書、楽しめていないかも?』をご覧ください)。
特に、速く読むことを評価しないように気をつけましょう。
繰り返しになりますが、まだ焦って一人読みに移行する時期ではありません。
一緒に楽しむこと、また、交互読みなどを通して、「文字を音にする」ことを大切にしてください。
2. 出来事をつかむ
本の理解については、描かれている出来事がわかっているかどうかを確認しましょう。
- 誰が、何をしたか
- 何が起こったか
こうしたことがわかっていない場合、本を読めていないかもしれません。
読み聞かせをしながら、お子様の目線に気を配り、意識がどこに向いているのかをチェックしてください。
意識がそれている場合は、指による視線の誘導や、内容に関する問いかけ・呼びかけが有効です。
また、眠気や疲れについては、読書時間そのものを見直しましょう。
読み聞かせの時には出来事をつかめるけれど、一人読みだとわからなくなるという場合は、文字と音が結びついていない可能性があります。
焦らず音読や交互読みを楽しみましょう。
3. 因果関係をつかむ
出来事がつかめるようになったら、次のような因果関係の理解が大切になります。
- なぜ、それをしたのか
- なぜ、それが起こったか
この段階では、登場人物・キャラクターの気持ちや意図が読めているかが重要です。
ただ、これは心情読解のような複雑なものではありません。他者の心情を汲み取れるようになるまでには、まだ成長が必要です。
ここでは、より単純な反応・因果関係の理解で十分です。
この時期におすすめの作家
書店や図書館には素晴らしい絵本がありますが、中でも、次の作家さんの本はこの時期におすすめです。
ジーン・ジオン
トミー・デ・パオラ
トミー・ウンゲラー
かこさとし
次回は、小2後半から小3後半の読書についてお伝えします。
「教育コラム」の記事
イメージ力と学びの関係
イメージは学びの本質です。
教科を問わず、学習にイメージ力は欠かすことができません。
たとえば、算数・数学において、条件や数字、文章をイメージ化しなければ、問…
作文が書けない。本を楽しめない。あるいは、読解問題が解けない。算数・数学の文章題が解けない。
それはもしかすると、心の中に「イメージ」がつくれていないからかもしれません。
イメージ力不…






