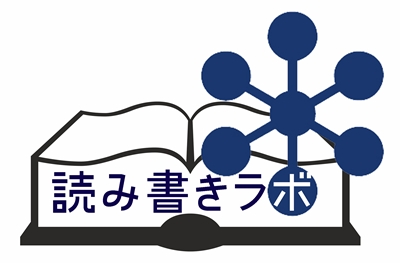
前回の記事では、読書習慣をつけるために大切なことをお伝えしました。
今回は、幼稚園から小学校一年生の読書(読み聞かせ)についてご案内します。
幼稚園~小1前半
ことばと本そのものに親しむ時期です。読み聞かせを十分に楽しみましょう。
この時期のあたたかな記憶が、本をより身近なものにしてくれる原風景となります。
焦って一人読みに移る必要はありません。また、無理に感想を聞き出そうとしたり、記憶させたりする必要もありません。
寝る前など、時間を決めてゆっくり楽しみましょう。
読み聞かせ

読み手は、無理に感情を込める必要はありません。ゆっくり、丁寧に読んでください。わかりにくい表現や、知識がないと理解できない箇所にきたら、その都度教えてあげましょう。「すごいね!」「これからどうなるんだろうね」など、物語の流れを滞らせない範囲で、一緒に楽しんでいることを伝えてあげましょう。
表紙・裏表紙などの絵も一緒に見ていきましょう。作者の名前も大切です。
視線と誘導
読み聞かせを聞くことに慣れてきたら、お子様の視線がどこに向いているのかに注意してください。絵本の挿絵のみを眺めているようであれば、まだ音読や一人読みに移るべきではありません。そのうちに、視線が文章を目で追うようになります。話し手より先に文章を読み終えてしまい、少し退屈しているようであれば、移行期であると言えます。
指さしで視線を誘導することもできます。気がそれている場合、また、文章に視線を誘導したい場合に有効です。
移行期
音読が大切になります。この時期に文字と音をしっかりと結びつけておかないと、読みが浅くなったり、早読みをしてしまったりする可能性があります。
- 文末を曖昧に読む
- イントネーションがおかしい
- だんだん読む速度が速くなる
- 一行飛ばしても気がつかない
こうしたことが見られる場合は、決して焦らず、音読を続けましょう。
その際は、一文を交互に読む、段落ごと交互に読む、ページを交互に読むなど、段階的に進めましょう。
ゆっくりとでも、よどみなく初見の文章を読めるようになれば、ひとり読みに移りましょう。
おすすめの本
この時期には、次のような本がおすすめです。
リズムを楽しめるもの
音の面白さやリズム、ことばの響きを楽しみましょう。
感覚が刺激されるもの/常識をくつがえすもの
子どもたちは、物が大きくなったり、しぼんだり、変形したりする絵本、または、現実にはない非常識な設定が大好きです。
おなじパターンの繰り返し
同じパターンの繰り返しで進行していく物語は、わかりやすいだけでなく、次の読書の段階に続く重要なステップになります。
すぐれた絵本はたくさんあります。しかし、すべてを買うわけにはいきません。
ぜひ近所に図書館を見つけて利用してください。おすすめコーナーでは、季節に合わせた本などを紹介してくれるでしょう。
次回は、小1から小2前半の読書についてご紹介します。
「教育コラム」の記事
記述指導の真のゴール!不自然な「てつなぎ」を避け、「ポンコツロボ」にも伝わる論理的な解答文の作り方から、すべての教科に通じる構造読解力の育て方までを解説。
記述の採点基準は「ズーム(抽象度)」と「ピント(客観性)」で決まる!設問の条件と解答欄から情報量を逆算し、ポンコツロボにも伝わる論理的なキーワードを選ぶ技術を解説。
「内容が不十分」から卒業!物語文は【状態・展開・結末】、説明文は【抽象・具体】のフレームで過不足なく情報をまとめる、論理的な解答作成メソッドを紹介。




